電気主任技術者の役割
自家用電気工作物の自主保安を確保するため、「保安規程」に基づき、設置者の電気スタッフとして、主に次の業務を行う必要があります。
- ① 電気設備技術基準への適合を維持するため、電気工作物を定期的に巡視、点検、測定および試験を行い設置者が取るべき措置について助言する。
- ②国の立入検査に立ち会う。
- ③従業員への保安教育を行う。
- ④電気料金の削減など経費節減に関する提案を積極的に行う。
- ⑤法令に基づく国への届出、報告書類の作成を行う。
- ⑥電気事故発生時の対応、再発防止のための点検および措置を行う。
https://www.sdh.or.jp/business/outsourcing_engineer/index.html#:~:text=%E2%91%A0%20%E9%9B%BB%E6%B0%97%E8%A8%AD%E5%82%99%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%9F%BA%E6%BA%96,%E3%82%92%E7%A9%8D%E6%A5%B5%E7%9A%84%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%80%82
四国電気保安協会 電気主任技術者の役割りと外部委託承認制度より引用
接近限界距離
特別高圧の充電電路における作業 労働者の身体又は、労働者の取り扱っている工具、材料と
充電電路との最短直線距離 接近限界距離を保たせなければならない。
22kV以下:接近限界距離 20cm
高圧充電部(6.6kV)接近限界:頭上300mm以上
足下600mm以上
軀(ク)側600mm以上
離隔距離
公称電圧に対する離隔をとること。
ただしクレーンブームなどで電路を絶縁防護することによって
距離内に近づくことが出来る。
| 100/200V | 1.0m |
| 公称電圧6600V | 1.2m |
| 公称電圧22000V | 2.0m |
※離隔距離以上を保って作業する。
絶縁用保護具

電気用ゴム手袋、保護帽等、作業者の身体に着用する感電防止用の保護具
電荷の放電
電力用コンデンサに放電コイルが内蔵
電路に変圧器が設置
どちらも停電年次の際には作業前に残留電荷を放電する
死活検電
- 保護具着用の上で検電
- 身近な相から一線ごとに検電
- 絶縁被覆の無いところで検電
断路器操作時の手順
送電停止 遮断器を切る→負荷側の検電→断路器開放
送電のとき 断路器投入→遮断器投入
停電作業時の措置
停電作業を実施するときは、当該電路を開路した後に、次の措置を講じなければならない。
(労働安全衛生規則第339条)
(※各MCCBの入・切状態を確認し、切状態のMCCBについては、マーキング等をし、明確にする事。)
イ 開路した開閉器に、作業中施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。
ロ 開路した電路が電力ケーブル、電力コンデンサなどを有する電路で、残留電荷による危険を生ずる恐れのあるもの
については、安全な方法により当該残留電荷を確実に放電させること。
(※安全な方法 残留電荷の放電は、短絡接地器具によって確実に行うこと。)
ハ 開路した電路が高圧又は特別高圧であったものについては、検電器具により停電を確認し、かつ
誤通電他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に
短絡接地すること
(※短絡接地器具取付のとき接地極側を取り付けた後電路側 標識の取付)
また、作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは
あらかじめ当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずる
おそれのないこと及び短絡接地器具を取り外したことを確認した後でなければ
行ってはならない。
●最高責任者が取り付け、取り外しを確認すること。
●受電することを予告する。
●短絡接地器具取外しのとき 電路側を取り外した後に接地極側 ※工具の確認は停電作業前、
作業終了後に 確実に確認する事。
●停電作業は打ち合わせた手順で行い、予定外作業は絶対に行わない。
万一、予定外作業を行う場合は、再度打ち合わせを行い、変更事を作業者全員に周知し作業を行う。
参考資料
高圧・特別高圧電気取扱者 安全必携 より一部引用

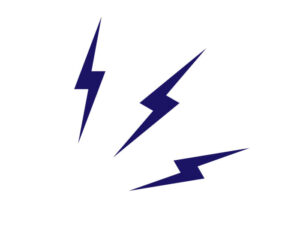
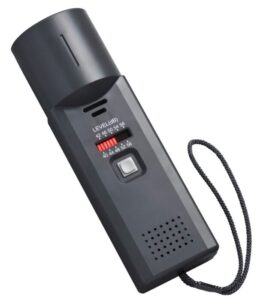






コメント