分電盤の内側に施設される分岐回路や開閉器の定格・個数などを表現した図面のこと
分電盤結線図を作成する目的
配線ルートの明確化: どの電線がどこから来て、どこへ接続されているのかを視覚的に示す。
機器構成の把握: 分電盤内に設置されているブレーカー(主幹ブレーカー、分岐ブレーカー)、漏電遮断器、端子台などの機器の種類と配置を示す。
接続方法の指示: 各機器の端子への電線の接続方法(極性、接地など)を具体的に示す。
安全性の確保: 誤配線を防ぎ、短絡や漏電などの事故を未然に防ぐ。
保守・点検の効率化: 将来的な増設や修理、点検作業をスムーズに行うために役立つ。

分電盤結線図の主な記載情報
分電盤結線図には、分電盤を製作するために必要な事項をすべて記入する必要がある
分電盤の全体構成: 分電盤の形状や内部の機器配置の概略図。
主幹ブレーカー: 電力会社からの引き込み線が接続される最初のブレーカーの種類、容量。
漏電遮断器 (ELB): 漏電を検知して回路を遮断する機器の種類、定格感度電流。
分岐ブレーカー (MCB): 各部屋や機器へ電気を供給する回路ごとのブレーカーの種類、容量、回路番号、負荷名称
(例:居室照明、エアコン、コンセントなど)。
端子台: 電線を接続するための中継点。端子番号などが記載される。
電線の種類と太さ: 各配線に使用する電線の種類(例:VVF、IVなど)と断面積(例:1.6mm、2.0mmなど)。
接地線: 接地線の接続箇所と種類。
配線ルートの記号: 電線の種類や本数を示す記号。
機器の記号: ブレーカー、漏電遮断器、端子台などを表す図記号。
線番: 各電線に付けられた番号で、図面と実際の配線を対応させるために使用されます。
注意事項: 工事上の注意点や特記事項。
図面情報: 図面作成者、作成日、図面番号など。
分電盤が複数多数ある場合、結線図で表現すると図面枚数と手間が増すため、電灯分電盤表という形で表現することもある。
分電盤結線図の読み方

主幹ブレーカーから追う: まず、電力会社からの引き込み線がどこに接続されているかを確認。
各分岐回路を確認: 主幹ブレーカーから各分岐ブレーカーへどのように配線されているか、電線の種類や太さを確認。
負荷名称と対応: 各分岐ブレーカーに記載されている負荷名称 (例:コンセントA、照明B)
が実際の建物内のどの機器やコンセントに対応しているかを確認。
接地線の確認: 各回路の接地線がどのように接続されているかを確認。
記号と照らし合わせる: 図面に用いられているブレーカー、漏電遮断器、端子台などの記号が
実際の分電盤内の機器と一致しているかを確認。
線番を確認: 実際の電線に付けられた線番と図面の線番を照らし合わせ、配線が正しいか確認。
分電盤結線図使用時の注意点
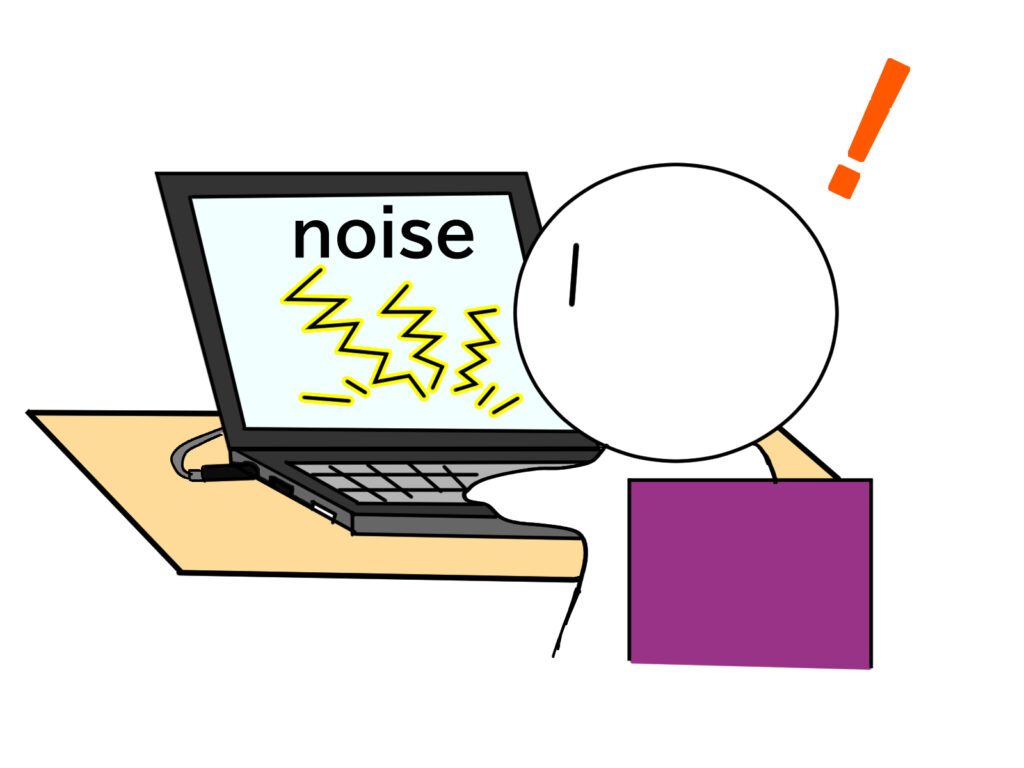
分電盤結線図は、専門的な知識を持つ電気工事士が作成・理解することを前提としている。
分電盤結線図は、竣工時の配線状況を示したものですあるため
後から配線が変更されている場合もあり、注意が必要
竣工から年数が経っている建物だと増設工事で分電盤結線図と現場の配線状況が異なっていることがある。

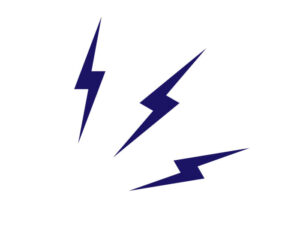
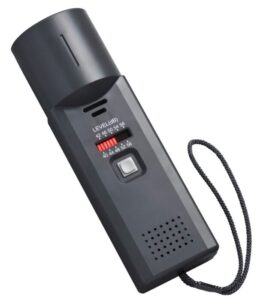






コメント